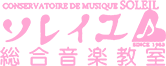ソレイユニュース 2025年4月号
-

ソレイユ総合音楽教室卒業生で藝大2年のNさんと『東京・春・音楽祭』に行ってきました。
『東京・春・音楽祭』は、3月から4月に掛けての1ヶ月間、上野公園の様々な施設で開催されるクラシック音楽の祭典です。
3月14日(金)、ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽でスタートし、4月20日(日)の演奏会形式によるオペレッタ『こうもり』で幕を閉じるまで、全75回(オペラなど重複する演目あり)のオペラ、リサイタル、そしてコンサートが開かれます。
会場は東京文化会館大ホール・小ホール、東京藝術大学奏楽堂、旧東京音楽学校奏楽堂などの音楽ホールの他、東京国立博物館や国立西洋美術館、国立科学博物館、東京都美術館などの、音楽と関係ない建物が使われるのも興味深いところです。
3月26日(水)に行われたのは、今年生誕100年を迎えた2人の作曲家、ベリオとブーレーズの作品によるコンサート。クラングフォルム・ウィーンという、オーストリアを中心に活躍する現代音楽専門の室内オーケストラと、現代音楽シーンにおいて最も抜きん出た演奏家のひとりと称され、世界で400曲以上もの作品を初演しているサラ・マリア・サン(ソプラノ)が、馴染みのない現代音楽を心地良い空間へと誘ってくれました。
ベリオ作曲『フォーク・ソングス』は、1964年初演の作品。現代的な音世界の中にも、ラヴェルの『5つのギリシャ民謡』を彷彿とさせる牧歌的な表現が耳馴染みの良い歌曲で、最後の歌『アゼルバイジャンの初恋』はディズニー作品そのもの❗最後の曲の意図は解らなかったけれど(アゼルバイジャンの民謡があのようにリズミカルなのかもしれない)、全曲を通して、いわゆる典型的な現代音楽の音とリズムの渦の中、思わず笑ってしまうアニメチックな締めくくりでした❗
また、民謡調の地声を駆使した発声方法も作品に幅をもたせ、正統的な発声とのコントラストも楽しめました。
変拍子や拍子の変化が頻繁に行われ、複雑な音とリズムが折り重なるブーレーズ作品は、『即興曲―カルマス博士のための―』と『ル・マルトー・サン・メートル』が演奏されました。
今回の室内オーケストラは、現代曲専門のオーケストラということで、読譜力高い才能を持つ人の集まりであると思うけれど、それにしても見事な演奏。子供の頃から現代曲に触れる環境の中、適切なソルフェージュ教育を施されて育ったと思わせる完璧な演奏に、幼児期からのソルフェージュ教育について色々考えさせられました。
ソルフェージュは大切、と伝えても、殆どの人に理解してもらえません。受験に必要だから仕方なく習っているという人もいるでしょう。
以前、藝大附属高校(藝高)に通っていた生徒に3月26日のコンサートで受けた衝撃を伝えると、藝高のソルフェージュ最上位クラスでは、現代曲も含めた様々な時代と作曲家の作品を初見視唱や新曲視唱に使用していて、編成も様々な室内楽曲なども楽器を使わずに歌っていたということでした。現代曲の初見もとても楽しいものだったそう。
目的がはっきりすると訓練も楽しくなるので、ご家庭での鑑賞ラインナップに、現代曲も入れてほしいと思います。
現代作品のファンたちによる、恐ろしい程の会場の静寂(音が鳴らない時間も表現のひとつ)も、作品の完成に大いに役立っていました。観客の質の高さに驚かされた夜でもあったのです。